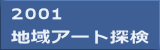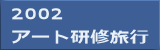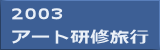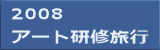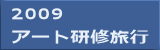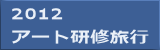M.A.P WORKS
|
PAGE POLICY 以下の内容は美術家ホームページとして統一性を欠き、表記もフランクに過ぎると受け取れるかも知れません。 |
|
M.A.Pは『都城をアートで面白くする企画集団』。宮崎県都城市在住の作家・教員・市役所職員をはじめ、 様々な業種の人々が『美術』『遊び心』でつながった1996年発足の非営利団体です。 私にとって作品制作は生きる方法を模索する手段であり遊びとは相容れないものですが、様々なものに出会い、多くの人と楽しみ・喜び・新しい見方を分かち合っていくこともまた大変重要な事です。ここに集まっていたのは、それを可能にする魅力的な人達でした。 惜しくも2013年4月に発展的解散となりましたが、 このページでその活動記録を御紹介します。 |
|
ARTSTREET 地域住民主導でM.A.Pが企画運営に関わったアートイベント。商店街を舞台とした展覧会としてはおそらく日本最初期のもの。利益を見込まない純粋な地域エンタメであり、地元ときわ通りを舞台に店舗内外の展示やワークショップ、コンサート、スタンプラリー等を行った。 |
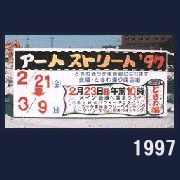 |
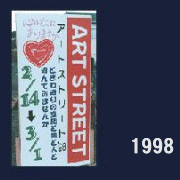 |
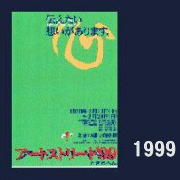 |
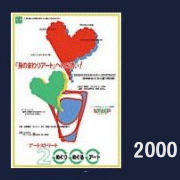 |
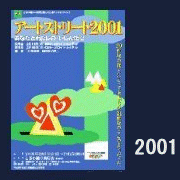 |
 |
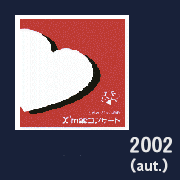 |
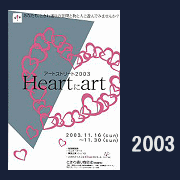 |
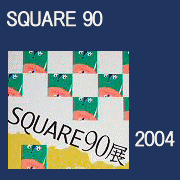 |
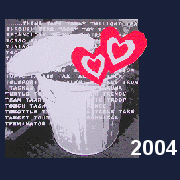 |
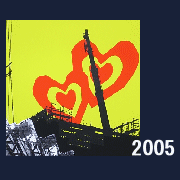 |
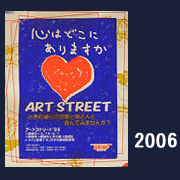 |
 |
 |
 |
 |
 |
2012 2012年11月18日(日) テーマ「古事記編纂千二百年」 (未取材) |
| 運営レポート |
|
以下の文章は『アートストリート』の運営に関わった都城市立美術館の学芸員・富迫美幸さんの97年度のレポートです。 あくまで美術館とは別の立場を貫き、作家の招聘もあえてせず、自らはサポートに徹しながら市民主体の美術展に賭けた彼女。 しかし、この形での実行でなければ現在「現代美術」と呼ばれているものは箱庭の中の出来事としてこの時代に生きる人々から 忘れ去られていくかも知れなかった…。私は常々同じような危機感を抱いていただけに大変な共感と頼もしさを覚えました。
どこからが美術?どこまでが美術? ~美の住み家~ 都城市立美術館 学芸員 富迫美幸
<アートストリート’97>(以下ASと略す)は、都城市立美術館の<メッセージ’97 南九州の現代作家たち>展(以下MMと略す/光野浩一出品)と同時に開かれた、民間有志(M・A・P) による企画であった。何を思っての仕掛けだったのか、振り返ってみた。 私たちは「遊びの場」を持ちたかった。「私たちの私たちによる私たちのための遊び」を。 舞台も出演者も裏方も全部まとめて、身近な暮らしの1シーンを自らの手で創ろうと考えた。 それが「生きている」ということではないか。REALに、VIVIDに、しかもPOETICに 遊べたら言うことなしである。 「額縁」に入っていれば美術品であるかというとそうではない。額に入ってないからといって 美術でないわけではない。例えば、こどもの作品を見ながら「これは額に入れて飾って置こう」 と思ったときなど、そこに価値判断(識別)の目が働いていることを思い出して欲しい。 「どこからが美術、どこまでが美術」という問いを、実は私たちは日頃からやっているのである。 そのレベルはさておいて、その問いに囚われるよりも、もっと初源的に(世事の利益「評価」は 二の次)「モノを創る」面白さを、自らの手で実感したいと願った。それはある意味で自分探しの 行為であり、自分たちのCOMMUNITY探しでもあった。 一方の<MM>は、「都城とその周辺地域にゆかりの作家を紹介するという都城市立美術館の 従来の路線上の企画で、その方針自体には何らの変化もない。時代を反映して中味が真新しい ものになったから、「変わった」のである。毎年、作家調査を続けていくと、おのずと美術界の 動向が見え、私たちのまちに生まれた作家たちもそうした時代の動きの中にいるのが分かってくる。 たとえ一地方の郷土作家紹介展であっても、もはや、一途に団体展さえ見ていれば全てを網羅 できる、とは言えない時代なのである。かつて、団体展が前衛でありまた全てであった時代の 美術家にとっては、理解を超える向きもないではなかったが、前衛の形も、美術家の在り方も、 時と共に移り変わるのである。
<MM>は、都城市立美術館が、ひとつのものさしをあてて作家を選んだ企画である。 そのものさしの是非を最後に測るのは、「客」としてのそれぞれの主体的な視線。いつでも、 ものさしは外から当てられるものなのである。しかし<AS>は、はかりを自らの内に求めた。 客寄せとか、企画に箔をつけるとかで、名の売れた作家を呼ぶことをしていないのも、誰かを奉る ことで、外的なものさしが<AS>の中に朕入するのを用心深く避けているからである。 ものさしで測られながらでは「思い切って遊べやしない!?」から。
美術館を舞台にプロが 演じた<MM>。気ままな遊び人たちが、大道芸よろしく、巷で「芸術」の真似事をした<AS>。 いずれも現在進行形だ。<MM>で、藤浩志が、暮らしの空間にあったはずの「喫茶店」を 美術館に「展示」したように、私たちは、「額縁」に閉じ込められている「美術」を、 逆に<AS>でもとの巷に放流しようとした。<AS>は、「アートが街に飛び出した(アートが 美術館から生まれる)」のではなく、「アートはもともと巷に(から)生まれる。アート ストリート(絵心通り)は、生まれるべくして生まれる。」と言いたかった。つまり、自身の 手の中にそれはあって、そこから生まれてくるのだと。藤浩志の「喫茶店」のように額縁に 入らないものであっても、それがそのまま巷にあって、たとえ、展示という形式で「美術館という 額縁」に入っているのではなくても、そのものがれっきとした美意識の賜物であれば、つまり それは「美」の領域にあるのだ、ということを言いたかった。<AS>と<MM>、この形式の 異なる二つの提示の仕方は、ひとつの事象のポジとネガである。それを同時にぶつけることで、 私は、美に関する私たちの意識のわだかまり(ねじれ)を浮び上がらせたいと思ったのである。 |
| 4年目 2000年の現状 |
|
「それでは只の遊びになってしまう。」
一スタッフの発言に我々ははっとした。いや!我々がやってきたのは、そしてやりたかったのは、そもそも「只の遊び」ではなかったか!?
アートストリートが回を重ねるにつれてからんでくる、様々な思惑や経済的な現実。規模の縮小を恐れる気持ちも確かに誰もが感じていた。 しかし、原点は「アートで遊ぼう。手弁当で集まって、我々自身、思い切り楽しもう。」ということにあったのであり、そもそも立派なアートイベントの成立に悩むなど、本末転倒の筈なのである。 前述のスタッフの苦言は、大きく膨れ上がってしまったこのイベントに、スタッフ自身が足をとられていたことを無自覚のうち、逆説的に問い正したものと取れよう。 (只の遊びになってしまう…。)いや、はなから遊びのはずだったのである。そして、それで良かったのだ。
スタッフは、5回目を迎えるアートストリートに向けて、まずは自分たちの姿勢を問い直すこと、肩の力を抜くことから始めた。 次回がどうなるかはまだ見えない。ただ、これだけは言える。たとえ小規模になろうとも、5回目のアートストリートはスタッフ自身が生き生きと活動する、内部から力漲る楽しいイベントになる。そしてそのエネルギーを面白がってくれる人たちは必ずいるだろう。
「アートのことはわからないと思っていたけれど」 会場近くのレストランで食事の折、店の人にいきなり話しかけられた。以前、派手なスタッフジャンパーを着て入ったことがあるので判ったのだろう。「なんとなく見続けていたら、ああ、いろんなものがあってもいいんだなと楽しくなりました。全部OK。写生なんかはうまくいかないけれど、自分にもなにかできそうな気がする。ずいぶんとものの見方が変わってきたと思います。ありがとう。」 周囲の人にも良い影響が出ている。暖かく見守られている。嬉しい限りである。
自分にとっての表現とは、自分の存在を確認するのに必要な、痛みを伴う投薬である。遊びとして楽しむことは出来ないし、ここでの出品は場違いだ。しかし、他者と向き合うことなしに作品は、自分は、そして美術は成立しない。閉塞はすでに死である。だから私はこのイベントを通じて人と関わる。美術と人との橋渡しを日常レベルで行う。 近年、美術界でもワークショップ形式の作品が急増中だが、本当に参加者の心に残るのは何だろうか。作家が良しとするのはどのような状態だろうか。プロが浅く思わせ振りな関係や無責任な期待を提供して終わるより、素人が遊びと割り切って工夫し、喜びを分かち合うほうがアートの在り方としてよほど真摯だと、私は思う。 作家の招聘やコンクールを行わず、利害も度外視した、一般市民が純粋に内なる欲求を形にした「アート遊び」。 それを可能にしているこの土地の人たちの元気やユーモア、ウィット、行動力に敬意を表しながら、関わり続けたいと思っている。
その試みが原点に帰り、力を得る。来年は重要な年になるだろう。 |